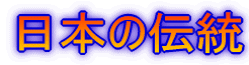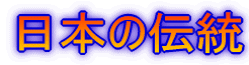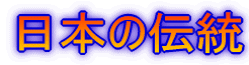
伊勢神宮では例年春と秋、神苑で舞楽を見ることができます。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
振鉾(えんぶ)
舞楽が始まるに先立ち舞台を清める舞です。
←写真をクリックで写真が拡大されます。
栄久舞(えいきゅうまい)
平成5年の神宮式年遷宮に奉祝されました。宮内庁の東儀文隆氏の作曲、薗広晴氏の作舞です。
←写真の拡大(写真を右クリック>リンクを新しいウィンドウで開く でBGMの中断なくご覧頂けます)
貴徳(きとく)
漢の時代に遊牧民族匈奴が漢に降った故事に由来しています。
高い鼻、鋭い目の白い「面」をつけて舞われます。
←写真の拡大 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
「蹴鞠」(けまり)が京都の蹴鞠保存会によって'02年5月5日に斎宮跡の
「いつきのみや歴史体験館」でイベントとして行われました。
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
鞠場
向って左奥の松が一番の上席です。手前右の柳が二番席、右奥の桜が三番席、手前左の楓が四番席です。
右の写真をクリックすると、写真が拡大します →
鞠渡し
蹴鞠(けまり)を始めるにあたり、作法による鞠の受け渡しが行われます。鹿皮で作られた鞠は、楓の枝にはさんで渡されます。
写真の拡大 →
蹴鞠
蹴鞠は一人が三度蹴ります。一度目は相手から受け、二度目は次へ渡す準備として蹴り、三度目に次の人へ渡します。
鞠を蹴る時、腰や膝は曲げずに蹴ります。かけ声をかけながら足の甲で蹴り上げるそうです。
蹴鞠は平安貴族に親しまれた、勝ち負けのないゲームです。
写真の拡大 →
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
三重県明和町の国史跡「斎宮跡」では、毎年6月の第1土、日曜日に斎王まつりが行われます。

斎宮・・・いつきのみや
鄙にはそぐわない雅な名をもつこの地は、かって伊勢の大神に仕えた斎王がましました所です。
斎王は、未婚の内親王や女王から占いで定められ、足掛け3年間の潔斎の後、斎宮へ旅立ちます。 |
 |
 |
群行
群行と呼ばれたこの旅は、平安時代には近江から鈴鹿の山々を越え伊勢国にいたる5泊6日の旅でした。 |
斎王制度
7世紀後半に天武天皇により定められた斎王制度は約660年間続き、斎宮は10〜11世紀にかけて隆盛を極めた後、南北朝時代の動乱のうちにその姿を消しました。
斎王は伊勢神宮に仕えるのが重要な努めでしたが、実際に伊勢神宮におもむくのは、年に3度だけでした。
斎王の存在は「伊勢物語」「大和物語」など数多くの古典文学に取り上げられ「竹の都」の華やかな面影を今に伝えています。
|
 |
 |
|